土日は、次女と孫二人が泊まりにきた。父親のAさんは、仕事が詰まっていて来れないとのこと。たまの孫の来訪はやはり待ち遠しく、掃除をしたり寝具の用意をしたり、料理の仕込みもあって、Mさんを中心に?非日常の時間を過ごす。
上の子Aくんは小1。元はといえば次女がプレゼントしてくれたのに、二人ではほとんどやらないWiiで、古いマリオをやるを楽しみにしている。来るとあいさつもそこそこにすぐに始めて、「1時間だよ」と母親に釘を刺されている。
下のHくんは3歳。クルマの中で寝てしまっていて、そのままMさんのふとんで寝てしまう。長い昼寝。
私は、父親のAさんと呑むのが楽しみなのだが、今夜は運転をしなくてもいい次女が付き合ってくれそうなので、散歩がてらワインを仕入れてきた。
5人での夕食のあと、大人3人の話題は子どものこと、学校のこと。
私たちにとってはもう遠い昔のこと。さまざま聞いていると30年以上の時間の隔たり、まさに隔世の感がある。
ここから映画備忘録。
『ゆめパのじかん』(2022年製作/90分/日本/監督:重江良樹/公開:2022年7月9日)
神奈川県川崎市で2000年に制定された「川崎市子どもの権利に関する条例」のもと、2003年7月に川崎市高津区にオープンした子どものための遊び場「川崎市子ども夢パーク」、通称「ゆめパ」を舞台にしたドキュメンタリー。約1万平方メートルの広大な工場跡地につくられた「ゆめパ」は、プレイパークエリア、音楽スタジオ、創作スペース、ゴロゴロ過ごせる部屋、学校に行っていない子どものためのスペースなど、子どもたちの「やってみたい」ことを実現させるさまざまな施設がそろう。この「ゆめパ」という場所を通じ、乳幼児から高校生くらいまで幅広い年齢層の子どもたちと彼らに関わる大人たちによって生み出される居場所の力、悩みながらも自身が考えて歩もうとする子どもの力が描かれる。監督は「さとにきたらええやん」の重江良樹。
隣同士の自治体だが、いろいろなところで川崎と横浜では違いがある。
横浜は、外から見ると外人墓地や山下公園、中華街やみなとみらい、どこか東京とは違う異国情緒があって、歌謡曲に歌われるような甘い幻想を抱かせる街だが、実際、そんなものは横浜のごくごくわずかな一部で、横浜の多くは350万人を超える人口を要する何の変哲もない巨大ベッドタウンだ。
それに比して川崎は、今でも京浜工業地帯の代名詞のようなイメージがある。横浜も京浜工業地帯の一部なのだが。
海辺のブルーカラーの街のように思われる川崎も、広い市域には全く違う相貌を見せるところがいくつもある。
横浜に住んで50年近くなるが、いわゆるヨコハマにではなく、市の周縁地域に住んできた身としてはそれほど強い愛着があるわけではない。毎年収める他市町村へのふるさと納税も返礼品目当てだけではない。
一方、横目で見てきた川崎には、横浜よりいつも一歩前に出ている新しさと動きの柔軟さを感じることが多い。隣の芝生、ではないと思う。
このゆめパもそうだ。横浜市にはここまでの発想はないと思う。
カメラが子どもたちによく馴染んでいる。撮影時間がかなり長いのだろうが、大人は別として(仕方がないが)子どもたちはかなり素の姿を晒してくれる。彼らが発する言葉もかなり面白い。
カメラはゆめパの中のフリースペースを中心に動いていく。何人かの不登校の子どもたちに焦点があてられる。
これがどの子もとっても魅力的だ。学校に行かなくとも、こんなふうに自分の力で創造的な生き方ができている。カメラはその辺りを生き生きと切り取ってくれる。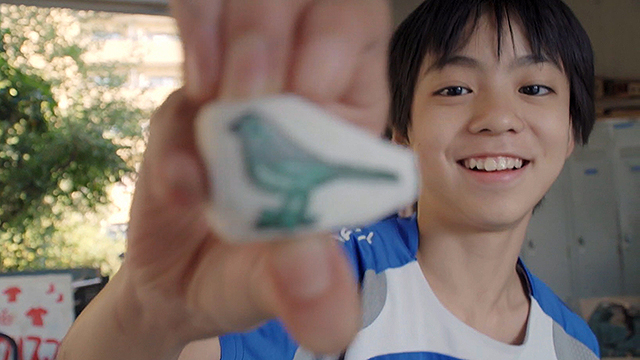
それはそれでいい。そういう子どもたちの思いや動きを受け止めてくれるゆめパの意義も素晴らしいし、それを受け止めながら、ゆめパで働く大人たちも魅力的だ。
ドキュメンタリー映画としての「ストーリー」はよくできているということだ。ここまでカメラが人々の中に入り込んでいるのは稀有なことだと思う。映画から子どもたちのもつ「力」のようなものが感じられるのも事実。
ただ不登校といっても、彼らのような子どもたちばかりでないのも現実だ。
取り上げられた何人かの子どもたちが、さまざまなものに自分の思いをぶつけていく、探していく姿を見るにつけ、不登校の状態にある子どもたちは、そういう子ばかりじゃない、目的など何も見つからず、無為に数年過ごす子どもたちもいるんだけど、という思いが浮かび上がってくる。
そんな子どもたちと付き合った時間が自分の中にあるだけに、夢パの中で動き回る彼らの生き生きとした表情が、私には少し眩しかった。
先日、労組・市民活動家として長く活動してきた友人が、80歳を前に「そろそろ隠居しようと思う」と周囲に伝えたところ「そうなんだ。それで、このあと何をやるの?」と言われたと苦笑していたことを思い出した。
60歳で再任用をせずに定年退職した時に、「何かやりたいことがあるんですよね」と言われてびっくりした。何もしたくない、ブラブラしたい、がホンネだった。今更したいことなどなかった。まだ変な色気が顔に出ているのかとがっかりした。
学校に行かない生徒に向かって、時に大人は同じように「何かやりたいことがあるんじゃないのか。やりたいことがあれば、どんどんチャレンジしていいんだよ」という。
それを悪いとは思わないが、やりたいことが何もない、何も思いつかない子どもも、いる。
映画の中の子どもたちのように、自分の夢を見つけ実現するために、学校を視界に入れずに苦闘する子もいれば、いけない学校を前に何年もじっと動かずにいる子どももいる。
大人は、子どもたちの思いを受け止めて、その支援をすることも大事だが、動かない子どもたちの時間に付き合うことも必要だ。
ないものねだりかもしれないが、そんな「ストーリー」が埋め込まれたドキュメンタリー映画もあっていいと思うのだが。