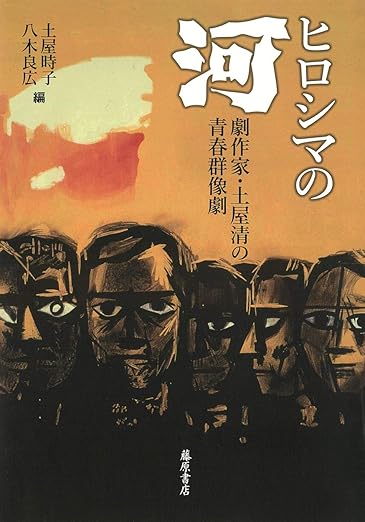3月も明日で終わり。2月の月末には飲む機会が増えたと書いた。
2020年の今頃は、全校休校。世の中はコロナに怯えていた。4年目になる。
何が変わって何が変わらないのか。自分の生活を見る限りは、大きく変わったことはない。4歳歳をとったというのは間違いない。
同じような毎日を過ごしている。
ほとんど何にも起こらない平板な毎日なのだが、振り返ってみると平凡なりにいろいろなことがある。
困るのは、みな忘れてしまうことだ。
なんでも憶えておけばいいというわけではないが、忘れ物をしたことを忘れてしまうような小さな不安がある。たぶん老化によるものだろう。
映画以外の日々の引っ掻き傷のような出来事、少しだけ書きつけておく。
3月5日、友人のAさん夫妻とランチ。
前回は瀬谷のフランス料理のお店。店が見つからず、クルマで付近をぐるぐる、遅刻した。住まいからさほど離れていないところに素敵な店があることに気がついた。
今回は、私たちのセレクト。遅れずに行こうと早めに出たが、Aさん夫妻はすでに到着。いつもきっちりとしたAさんたち。
『蕎澤』のそば懐石。昼間の営業がおわって13時半から。
何年も通っているが、初めて。
前菜(そばや豆腐を材料に)
そばの実の料理
そば粉の料理
揚げ物
種物のそば
もりそば
デザート
こう書くとさっぱりしたもののようにも見えるが、ゆっくり味わうそばと豆腐、野菜。
1時間半ほどのランチがとても豊かなものに感じた。おそるべし蕎澤、である。
食べ物もの話が続く。
3月15日。Mさんの誕生日。71歳。
9階の”あつぎのえいがかんkiki”で『瞳をとじて』を見たあと、B1のアドマーニで二人で食事。何度も来ているが、いつも満足のイタリアン。飲み放題付きのコース料理。生ビールは格段に美味いし、ワインもそこそこ。何より接客が温かい。
帰途に1時間余かかるのが玉に瑕、ほろ酔いのまま。
3月16日。次女の息子のA人くん(9歳)の空手の演武を見に保土ヶ谷公園へ。前回の9月に比べ、上達ぶりがよくわかる。
クルマを停めてすぐにAくんと空手クラブの世話人の方に会う。
「A人くんのおばあちゃんとおじいちゃんですか?」
「そうです、いつもお世話になっています」
こういう会話がいまだに恥ずかしいのはどうしてだろうか。
父親のAさんは土曜出勤。演武終了後、弟のH人くんと4人で保土ヶ谷郵便局の隣のかごの屋というお店でランチ。Mさんの誕生日ということでご馳走してくれる。私がポロポロとだらしなく食べこぼしをするのを、4歳児のH人くんが面白がっている。
3月17日。
東京、台東区三ノ輪で人間と発達を考える会の研究会に出席。会場は自立支援センターふるさと会のビル。
土手通りを東に歩く。スカイツリーが大きく見える。歩いて10分ほど。
三ノ輪というと「三ノ輪の親分」という言葉が口をついて出る。銭形平次だ。
地下鉄日比谷線の一つ前の入谷を通ると「おそれ入谷の鬼子母神」、が出てくる。つづけて「なさけありまの水天宮」が出てくる。
先日、友人のSさんに用事があってメールをしたら
「今、土手の伊勢屋に来ています」とのこと。
「10時20分着いて並んで8人目でした。開店前には40人くらい並んでいました」とのこと。
土手の伊勢屋はよく知られた天丼の店。前から一度は訪れたい店の一つ。
本日の研究会のテーマは、横田泉(みつる)さんの『精神医療のゆらぎとひらめき』(日本評論社・2019年7月刊)
精神科病院に勤務しながら、いくつかの雑誌に書かれた文章をまとめた本だが、たくさんの気づきを与えてくれる本。
「患者の利益にならない医療はやらない」という、ごく当たり前でありながら、現実にはありえない医療を、目指すのではなく実践している方。
精神医療については、現役の教員時代にもいくつも接点があったが、こんなふうに公言して実践している方は、そうはいない。
この日は、リアルでは7名の方の出席。横田さんはじめ3人の方が沖縄からオンラインで出席。同じ精神科医の滝川一広さんもそのお一人。
この本のあとがきに3人の方が登場する。これが大変に興味深かった。
お一人は、前書きを執筆している作家の木村友祐さん。私は今まで2冊、この方の作品を読んだ。気になる作家の一人。
横田さんは木村さんの『イサの氾濫』を引いて、「自由と非暴力という最前線の同士だ」と書く。
精神科病院の医師として、横田さんは一度だけ患者を薬を使って入院させたことがあるという。若い頃のことだが、横田さんにとってこれが自ら医療に向き合う上での一つの桎梏であり、出発点であるという。
患者にとっては医師は権力そのもの。その権力を行使しない、暴力を使わない医療について、本書は大変に深く広く鋭い知見をもって展開している。
『イサの氾濫』を読んだ。そこには「東北震災の際に日本中を飛びまわった甘言、欺瞞、偽善にたいする怒りと反撃が見事に描かれている」(横田さん)。
震災から距離をとっていた主人公が、久しぶりに八戸に帰り、荒くれ者の叔父勇雄(イサ)について知る。その荒れの中の孤独と悔しさを、自分の中に蘇らせ・・・。
収録されている短編「埋み火」もよかった。
今、『野良ビトたちの燃え上がる肖像』と『聖地Cs』を読んでいる。
2人目は写真家の鬼海弘雄さん。この本のとびらの写真は、鬼海さんの「登戸2001」と
いう作品。

拡大してみてみてほしい。なんとも惹きつけられる写真。
鬼海さんの写真集2冊とエッセイ1冊を図書館で借りた。
居間のテーブルに置いておいたらMさんが手に取っていた。「すごいね、この写真集」。
人の顔がこんなふうにふうにおもしろいものだということに今更ながら気がつかされた。
横田さんは鬼海さんのことを「自由人」と呼ぶが、「自由人」についてこんなことを書いている。
・・・私は職務上、自由人と顧客関係を長年にわたり結んでいるが、彼らとの友好関係を保つためには自分もそれにふさわしい医者でなければならない。吹けば飛ぶような「専門性」や「権威」には頼らない。ひどいことは言っても嘘はつかない。無理難題に愚痴は言ってもギブアップはしない。すぐに感情的になってしまうけれど、あとで反省してお詫びする。・・・
これを読むだけでも横田さんの人柄がよくわかる。
現役の教員時代、私もこれに近い感覚で生徒と向き合おうとしていた。違うのは、横田さんはそのまま実践し、私は反省ばかりしていたことだ。
3人目は、この本の編集者森美智代さんである。森さんは日本評論社の社員で雑誌『統合失調症のひろば』をつくった人。この雑誌は横田さんに言わせれば、
・・・(「統合失調症のひろば」は)もはや統合失調症という枠組みをはるかに超越し、「自由人のための自由人による自由の雑誌」になった。どのページを開いても自由のかおりがたちこめる。「ひろば」の編集会議に行くと、全国から自由人たちが集まりかって気ままなことを話す。話だけではない。絵画、コラージュ、演劇、音楽とおよそ「会議」には似合わないアートが繰り広げられる。何も決まらない編集会議はとてもここちよい。彼女を通して、本当にたくさんの自由人と巡り合い知恵と勇気をもらっている。そもそもこんな素敵な本ができたのも彼女の奮闘のおかげだ。こんなありがたいことはない。・・・
編集者と著者の関係を超えた出会いの僥倖。
(統合失調症のひろばは現在休刊中)
私はかつてこの本の版元である日本評論社の『こころの科学』という雑誌に隔月で3年間小文を連載していたことがある。
原稿用紙8枚程度の文章に毎回のように呻吟するのだが、苦労はしても無骨で繊細さのない文章は編集者泣かせ。担当の編集者は原稿を見ると毎回のようにこう言ったものだ。
「私はいいと思うんですけど、うちのカミさんがねえ・・・」
のちに「カミさん」におめもじかなうことになるのだが、その方が実はこの森美智代さんだった。
今となれば、おつれあい森さんのダメ出しはよくわかる。
横田さんの文章のなんと端正なこと。私の文章とは比較にならない。
これは、同じ精神科医の滝川一広さんにも通ずることだが、きわめて論理的であるのに文章に温かみがあり、時に怒りがあるのにどこか静謐なのだ。
私のようなストレート一本槍とは違う文章の懐の深さのようなもの。
この3人と横田さんの4人でコラボでできた「自由の書」がこの本だと横田さんはいう。
精神医療について書いた本を「自由の書」だという横田さん、そんじょそこらにいるドクターではない。
もし横田さんの謦咳に接したいという読者の方は、次の動画をご覧いただきたい。
www.youtube.com
2019年のもの。お人柄と主張がよくわかる動画だ。
さてさて、研究会は若い精神科のドクターの方の大変に精細なレポートを元に、沖縄とと東京を結んで4時間近く行われた。
やはり外に出かけて行って勉強することが刺激になるようだ。こういう場に出させていただいて感謝している。
3月21日。
卒業生のAさんと長津田のサイゼリアで会う。まだ生まれて間もない男児をベビカーに乗せてAさん登場。4年ぶり。4年前は独身で子どもはいなかった。
彼女は今イラストレーターと西洋占星術の占い師の兼業。占いは某雑誌のネット版を担当している。
卒業して16年。頻繁ではないが、何度か会った。
偉そうな言い方かもしれないが、人はこんなふうに自分をつくっていくのだなと、その落ち着いた挙措を見て思った。いつでも「今」がその人の人生の集積なのだと思う。
私の人生を見てもらった。
終わりに近づいている人生をあとづける占い。思いがけず「当たっている」ことも。
3月22日。
毎年恒例の広島在住の子どもの本作家の中澤晶子さんを囲む会。主催は「横浜・広島修学旅行研究会」。大人数で集まるようになって15年以上になる。中華街、牡丹園というお店が常宿。
今年も横浜だけでなく、大阪や東京からの参加者があった。こんな私的な研究会が長続きしているのは、広島現地で修学旅行生を案内してくださる中澤さんの存在がなんと言っても大きい。昨年の「オトナの広島修学旅行」でも全面的にお世話になった。
昨年は『ひろしまの満月』で第70回産経児童出版文化賞の産経社章を受賞。中学生とひろしまの関わりを描いた『ワタシゴト』3部作も完結した。
この4月から東京書籍の6年生の国語の教科書に「模型のまち」が掲載されている。
広島のどうしようもない行政と闘う市民運動や文化活動にも相変わらず八面六臂の活躍。
3月24日。東京、練馬のギャラリー古藤で
<朗読劇> 「神部ハナという女の一生」
2人で出かける。
いろいろなところで耳にする「ギャラリー古藤」は、武蔵大学正門の筋向かいにある。
元NHKのディレクターで武蔵大学教授の永田浩三さんとの関係があるからだろうか。
この日も永田さんが朗読劇のあとの鼎談に出られていた。
入り口でパギやんこと趙白さんにお会いする。今日は照明をするらしい。
神部ハナを演じるのは、土屋時子さん。広島ではよく知られた方。
広島文学資料保全の会代表で、hifukusyouラジオの司会も務めていらっしゃる。
そして『ヒロシマの「河」 劇作家・土屋清の青春群像劇』の編者。土屋清さんのおつれあいだ。この本に趙白さんも寄稿していたと記憶している。
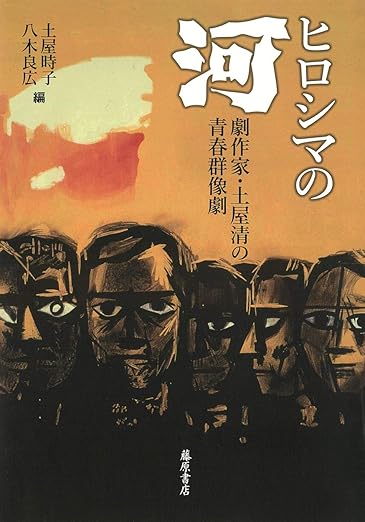
朗読劇とはいえ、照明や音楽、芝居も取り入れた本格的なもの。神部ハナという戦後を生きた一人の助産婦の悲劇を描いている。
作者は劇団民藝がロングラン公演を続けている『泰山木の木の下で』の作者小山佑士。泰山木の・・・の底本が神部ハナ、である。
終了後、土屋さんにご挨拶する。