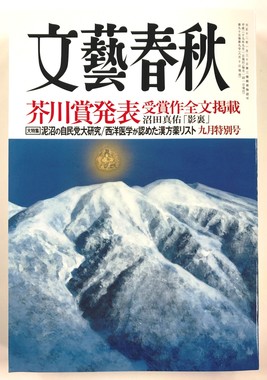温又柔の『魯肉飯のさえずり』(2020年)が面白かったので、すぐにエッセイ集『台湾生まれ日本語育ち』(2016年)と小説『真ん中の子どもたち』(2017年)を読んだ。前者は第64回日本エッセイスト・クラブ賞を受賞し、後者は芥川賞候補となった。
私は記憶にないのだが、温又柔作品は受賞はしなかったが、審査員宮本輝氏の選評が物議をかもした。
ネットに出ているJcastニュースの記事をそのまま紹介する。
第157回芥川賞に「真ん中の子どもたち」という作品でノミネートされた台湾生まれの作家・温又柔(おん・ゆうじゅう)氏(37)が、同賞の選考委員を務めた作家・宮本輝氏の「選評」にツイッターで怒りを露わにしている。
「もどかしく悲しく怒りに震えました...」――。宮本氏の選評が2017年8月10日発売の月刊誌「文藝春秋」に掲載されて以降、温氏はこうした怒りのツイートを何度も投稿している。一人の作家をここまで立腹させる選評とは、いったいどんな内容だったのか。
「他人事を延々と読まされて退屈だった」
第157回芥川賞は7月19日に選考会が開かれ、沼田真佑(しんすけ)氏(38)の「影裏(えいり)」が受賞作となった。選考委員を務めたのは、宮本氏をはじめ、奥泉光氏、村上龍氏、山田詠美氏ら現代文学を代表する作家10人。
温氏は台湾・台北市で生まれ、3歳の頃に東京に引っ越し、台湾語混じりの中国語を話す両親のもとで育った。候補作となった「真ん中の子どもたち」は、台湾出身の母と日本人の父を持つ若者が自らの生き方を模索する姿を「母語」をテーマに描いた作品だ。
この作品に対する宮本氏の選評は、次のようなものだった。
こうした宮本氏の批評について、温氏は掲載誌の発売翌日にあたる8月12日未明(日本時間)、ツイッターで怒りを爆発させた。「どんなに厳しい批評でも耳を傾ける覚悟はあるつもりだ」と前置きした上で、
と指摘。続くツイートでは、「おかげさまで炎は燃えあがる一方。ここが『対岸』かどうか、今に見ててね」と挑戦的な一言を送っている。
「選評を読んで絶句した」
温氏はさらに、12日早朝にも「あぁ、また呼吸が浅くなる。半日たつのに、怒りがまだしずまらない。こんなに怒ったのはひさしぶりだ」と投稿。ただ、温氏の憤りに共感した一般ユーザーのつぶやきにリプライ(返信)する形で、
と前を向くような言葉も寄せている。
一連の温氏の投稿はインターネット上で注目を集め、ツイッターやネット掲示板には、
など、温氏に共感する意見が相次いでいる。
そのほか、作家の星野智幸氏は12日のツイートで「これはもう差別発言」と指摘、詩人の文月悠光(ふづき・ゆみ)氏も「この部分、私も選評を読んで絶句した」と同日にツイートしていた。
「おかしなことは書いてない」との声も
ただ、他の選考委員の批評を見ても、温氏の作品に厳しい意見はあった。例えば、次のようなものだ。
こうした他の選考委員の意見を踏まえた上で、インターネット上には、
と選評全体としては「問題ない」とみるユーザーも出ており、全体として賛否が分かれている印象だ。
なお、温氏は17日に更新したツイッターで改めてこの問題に言及。「作品への評価ならどんな叱咤激励にも心して耳を傾ける」とした上で、
と振り返っていた。
私が意見を求められているわけではないが、もし聞かれたらどうこたえるか。
「宮本輝、馬脚を現したな」である。
私が若いころ(30代前半頃まで)、若い頃の宮本輝作品はそこそこよりどころだったことがある。しかし、いつの間にか読んでも何も感じなくなり、読まなくなった。作家がいいものをずっと書き続けることって大変なことなんだと思った。いつしか宮本は文壇の大御所の立場に立つようになった。
「殿」のような立場だから、新しいものはなかなか入ってこない。自分が理解できないものはぺけ。
いつしか
『日本人の読み手にとっては対岸の火事』
『当時者にとっては深刻だろうが退屈だった』
として自分の読み方を日本人を代表するものとして提示するようになる。作家が、表現を生業とする人が、何かを代表するような物言いをするようになったら終わりだと私は思う。この選評は単なる好き嫌いを言っているだけだ。
「厳しい選評を書いてやったぜ」と思っていたら、作家本人からだけでなく、他の小説家からも批判が飛んできた。星野智幸氏、よく言った。自分の作家活動と主張がしっかり地続きだ。あ、宮本もそうか。
しかし、他の審査委員も宮本を擁護する。
吉田修一に言いたい。「母国語とアイデンティティーという切実なテーマがブルドーザーのように迫って」くる作品はだめなのか?読者が怖くって飛びのいてしまう作品はダメな作品なのか?
島田正彦に言いたい。「エッセイと小説は別物だろう?自分のテーマを映画や音楽、小説やエッセイ、さまざまな表現媒体で表そうとするのはいけないことか?決めるのは読者。」
宮本輝には、温の「文学って、その対岸へと橋渡しをするようなものではないの?すべての物語は『他人事』だよ」で十分だろう。
この作家たちには、日本語で書かれた多くの在日韓国人作家たちの脈々たる文学の貴重な作物が目に入ってこなかったのだろうか。
近代日本が侵略によって植民地化した多くの国々で、またそこから日本にわたってきて、日本語でものを考え書いてきた人々の文学や思想が気にかかったことはなかったのだろうか。
ネット上のことばとして
「対岸の火事だと思っている人の意識を変えることができなかった、力不足な作品だ、と言っているのであり、選評としてこれはアリ」
「宮本輝氏の選評は特におかしなことは書いてないと思う。ただ言葉足らずな印象を受ける」
というのが紹介されているが、宮本の選評は作品論にはなっていない。自分の理解できないものを忌避しているだけではないのか。力不足な作品だというのなら、その部分を具体的に指摘すべきだと思う。
「宮本選評は言葉足らず」こうした擁護論は、論外。宮本も恥ずかしいだろう。作家が「言葉足らず」と言われたら立つ瀬がない。
日本の文学というあいまいなものはなく、あるのは日本語で書かれた文学であり、書き手はもちろん日本人限定ではない。
温の生まれた台湾は、もともとの現地で使われた台湾の部族のことばがあり、中国に近い言語もある。それは蒋介石が持ち込んだ中国語とも違うし、もちろん現在の北京語のような中国語とも違う。それらは似ているが別のことばだ。そこに植民地時代の日本語が加わる。
親は日本語を話せなくても祖父母は日本語を話せる。親は、日本に親近感をもたなくても祖父母は日本が大好きという場合もある。もちろんそんな簡単なことではないのだが。
そして現在の台中関係の中で、独立傾向の強い政治が影響して、台湾人による独自の台湾語に台湾の人々はアイデンティティーをもつようになる。
彼女の作品でたくさん教えてもらった。
その一つ、中華人民共和国と台湾の国境線がどこにあるか、私は彼女の本で初めて知った。驚いた。
日本と台湾の国境については知っていたが。知らない人は、ぜひ調べてみてほしい。
台湾人の記者に「あなたは自分の居場所はどこだと感じますか」と質問されたとき、温は「わたしは日本語に住んでいます」とこたえる。
温は続けてこう書く。
「たぶん日本語で訊かれたのなら、もう少し照れがあったかもしれない。中国語でのやり取りだったからこそ、そう言い切ることを自分に許せたように思える。改めて宣言するまでもなく、それを「母国語」と呼ぼうと呼ぶまいと、わたしが自分の思考の杖として最も頼りにしている言語は、日本語なのだ。「母国語」に限りなく近いけれど、生まれた時からわたしのものではなかった言語。/日本語とそのような関係を結ぶ自分が、台湾人である、という「偶然」は、近頃ますます「必然」めいてくる。台湾の歴史の中に日本語という言語が縫い込まれている、という事実は、台湾人でありながら、日本語で書く自分を認識すればするほど、わたしの中で重みを増してくる。」
そして遠く植民地時代の作家に思いをはせる。
「「帝国」が強いる「国語」と、「植民地」の「母語」。巧みに使いこなすことで社会的な権力を獲得する道が開けるのは、明らかに前者の言語である。逆にいえば、それを習得しない限り、みずからの「コトバ」を発する機械は半永久的に奪われ続けてしまう。/こうした非対称的な二重ー場合によっては三重、四重ーの言語状況に陥ることになったのが、植民地化にある「母国」を生きる作家たちだ。/当時の台湾では、のちに台湾語と呼ばれることとなる門(中に虫)南語や客家語などを「母語」とする人々の多くが、帝国の言語である日本語で小説絵を執筆していた。
ー我住在日語(私は日本語に住んでいます)。
かつて、余儀なくそこに住まわされていた人々のことを思って、わたしはにわかに落ち着かなくなる。あなたの居場所はどこだと思いますか? と問われて、中国語で日本語ですと答えるわたしを、日本統治期の台湾で日本語で表現せざるを得なかったさっかたちは、呑気なものだねと呆れるだろうか?
まさに彼女自身が歴史的存在であり、その彼女が住んでいるのが「日本語」であるという現実、こういう現実に対し私たち日本語を母語とする人間は敏感ではない。
台湾や韓国、朝鮮だけでなく、戦前からの南米と日本のつながりは長く深いが、現在でも「日本語に住む」在日ペル―人やブラジル人がたくさんいる。
温が「日本語」に住むといった時、それは作家としての研ぎ澄まされた日本語だが、一般の作家でもない普通の人間にとっての日本語とは、たとえば濁音が苦手が朝鮮人の日本語であったり、「サッカーを遊ぶ」といった言い方が一般的になっている日本語であったりする。
日本語に住む、という感覚を超えて、日本語を拡張する、といったいわば多様な日本語のありようが存在すると考えてはいけないだろうか。多様な英語があるように、多様な日本語がある。方言と同じようにブラジル系の日本語や韓国系の日本語、ということだ。
中国人が台湾語を中国語と認めないといった権威主義ではなく、誰もが住める日本語という発想があってもいいような気がする。
そんなことを考えさせられた。
小説の話の戻る。小説としては『真ん中の子どもたち』より3年を経た『魯肉飯のさえずり』のほうが完成度が高いと思う。しかし、温の「日本語に住む」という独特の感覚は『真ん中の子どもたち』のほうが時間的に近い。『魯肉飯のさえずり』は、すこし整理されすぎているように思えた。